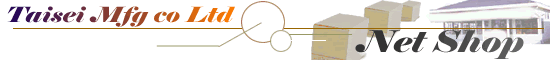
よくお客様に聞かれる質問で、撚りロープと組み紐の違いは?というご質問があります。
(三つ撚りなどの紐を便宜上ロープと定義しております)
用途によってどちらのタイプが良いのかという質問には、お客様に選んでいただくしかないのですが、
簡単に違いを記載してみたいと思います。
★まずインターネット辞書で組み紐とロープ(撚り紐)を検索してみると、
| 組み紐(金剛打ちや16打ち) | ロープ(撚り紐) | |
| goo 辞書(大辞林) | 数十本の糸を一定の方式で交互に交差させて組んだ紐。羽織紐・帯締め、その他装飾紐として用いる。組緒。打ち紐。 | 綱。縄。麻・針金などを太くより合わせた綱。 |
| Yahoo!辞書(大辞泉) | 複数の糸を組み合わせて作ったひも。組緒(くみお)。打ち紐。 | 縄。綱。繊維または鋼線をより合わせた、じょうぶな綱。索。「ワイヤー―」 |
| ウィキペディア | 組み紐(くみひも)とは、手芸の一種で、糸を編んでひもにしたもの。 >> さらに詳しく | ロープとは縄(なわ)のこと。>> さらに詳しく |
上記のように一番の違いは原料となる繊維の束を幾つ使うかということが、両者の大きな違いとなります。
ロープは三つ撚りロープを代表として、その前後の数の撚り数が一般的であるため、繊維束は2組〜4組程度になります。
ところが組み紐は8組から多いものでは32組の繊維束で織り上げていきます。(後に説明する金剛打ちは12組)
組み紐は多くの繊維束をからめる必要性から、それぞれの束を交差するような編み方(編組)をするため、
撚っているだけのロープに比べ、糸をほぐそうとすると非常に困難なことになります。
以下に編組していることの長所と短所を挙げてみます。
| 組み紐の長所 | 組み紐の短所 |
| 各繊維束が複雑に編みこまれているため、繊維がほぐれにくい。 | ほぐれにくいため、ロープでの末端処理をまねることはできない。 |
| 組み紐の中の一種類である金剛打ち紐は、編みこみの凹凸を極力なくした編組方法であるため、切断面が真円に近いものになる。 | 撚りロープの凸凹を必要とする場合は、逆に短所になってしまうが、意識的に凹凸をつけている編組方法もある。 |
| 編みこみにより、各繊維束は他の繊維束の内部にもぐりこむため、繊維束が常に表面上にさらされるロープに比べ、摩擦などによる磨耗が軽減される。 |
|
| 編み込みが複雑なため、撚っただけのロープに比べ見た目が美しい。 | 撚り紐の最大長所として、安価、サイズ(太さ)が多彩という点がある。 |
| ロープは一方項への捻りによって製造されるため、完成品のロープ自体がねじれやすくなってしまう。<捩れ(キンク)> それに対し、左右からの繊維束が編みこまれる組み紐はねじれが発生しにくい。(皆無ではありません。) |
なおインターネットで調べている際に、
(金剛打ちという組み方は2度組む方式なので 耐久性がありロープによくある組かたです。)
(金剛打は芯がなくても断面が真円に近く、耐摩性に優れる。 )
という記述を見かけましたが、正確には上記は間違えです。
金剛打ちは2重に編む方法ではなく、編み込みのパターンが他の組み紐と違うということです。その中では2重に編組する場合もありますが、全てではありません。
また金剛打ちは基本的には芯材になる繊維を入れます。そうしないと太くなるにつれ、編みこみが崩れてしまう編組方法なのです。
また辞書でも細いものは組み紐、太いものはロープと記載しているものもありましたが、これも正確には間違えです。
上記に記載したように、余りにも太いものは組み紐での製造は困難になりますが、通常利用するサイズはどちらのタイプも存在します。